季節風|KISETSUFU
春 ツバメ記念日
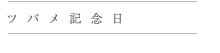
午前十時半。電車の運行ダイヤは間が空いて、十五分に一本の間隔だった。会社に着くのは正午過ぎになる。会議の結果がどうなったのかは知らない。欠席を電話で伝えたときの部長の「まいったなあ……」の声の響きは、おそらく一生忘れないだろう。だから![]() いまは、思いだしたくない。
いまは、思いだしたくない。
やっぱり家に帰ろうか。ため息をついてうつむいたとき、横から声をかけられた。
「すみません」
おばあさんだった。
「はい?」と振り向くと、杖をついたおじいさんがおばあさんの隣にいた。
「ここ、一緒に座らせてもらってもいい?」
「はあ……」
ベンチは四人掛けなので、空きはある。ただ、ここはホームの端だ。おじいさんの足が不自由なのに、どうしてわざわざここまで来たのだろう。
訝しむわたしの胸の内を読み取って、先におじいさんを座らせたおばあさんは、自分が座る前に向かいのホームの屋根を指差した。
「あそこ、ツバメの巣があるんです」
言われて初めて気づいた。ほんとうだ。屋根の柱と梁が交差するところに、ツバメが巣をつくっている。
「ここのベンチが、いちばんよく見えるんですよ」
おばあさんの言葉を引き取って、おじいさんも「このまえ、卵がかえったばかりなんだ」と皺だらけの顔をうれしそうにほころばせた。
「……ずっと見てらっしゃるんですか?」
「そうよ」「もう何年もな」
「ツバメを?」
「そうよ」「毎年のことだ」
「じゃあ、電車に乗るついでじゃなくて、わざわざ……」
「そうよ」「定期券もそのために買ってある」
二人の受け答えの呼吸はぴったりだった。長年連れ添った夫婦ならではの阿吽の呼吸ができているのだろう。
すごいなあと感心して、そのぶん少し寂しくもなって、目尻に残った涙を指で軽く拭ってから、あらためてツバメの巣に目をやった。
ほんとうだ。ヒナがいる。
と、そこに線路の上の空をすうっと滑るように親ツバメが飛んできて、巣の縁に止まった。われさきにと口を開くヒナに、親ツバメは順番に口の中の餌を与えていく。
持ち帰った餌が終わりかけた頃、もう一羽の親ツバメも戻ってきて、最初の親ツバメは入れ替わるようにまた空に飛び立っていく。
ツバメの雄と雌の見分け方なんて知らない。でも、つがいなんだろうな、この二羽。
おばあさんはひとりごとのように、「ツバメっていうのは働き者だからねえ」と言った。
おじいさんもうなずいて、「夫婦そろって、よく働く」と応えた。
「ねえ」![]() おばあさんは、わたしに向き直る。「わたしたち、駅前でお店をやってたの」
おばあさんは、わたしに向き直る。「わたしたち、駅前でお店をやってたの」
おじいさんはツバメを見つめたまま、「八百屋だ」と話を継いだ。「いまは息子の代でコンビニになったがな」
知ってる。何度も買い物をしてる。
「八百屋の頃は忙しくてねえ、わたし、こう見えても五人も子ども産んだんだから」
「貧乏人の子だくさん、っていうんだ」
「いちばん大変なときは二人いっぺんにおんぶして、チビちゃんは片手で抱っこしておっぱいあげながら、カボチャやら白菜やらを袋に詰めてたんだから」
おばあさんは懐かしそうに、うれしそうに微笑みを浮かべて言う。おじいさんは少し照れくさいのか、ムスッとした顔になって「ツバメのつがいと同じだ」と言った。
「ツバメってねえ、夫婦で巣をつくるのよ。卵も夫婦で交代して暖めて、ヒナにごはんを食べさせてやるのも夫婦でかわるがわる……ほら、また交代してる」
餌を捕ってきた親ツバメが飛んでくる。まるで競泳のリレーみたいに、巣に止まっていた親ツバメは翼を広げて飛び立つ。
「一日に何十回も餌を運んでくるの。お父さんツバメもお母さんツバメも」
わたしは黙ってうなずいた。ツバメの生態なんてなにも知らなかった。だからこそ、ひと息つく間もなく餌捕りと餌やりをひたすら繰り返す二羽の親ツバメの姿が、たまらなく愛おしくなった。
「夫婦二人でお店をやってると、そりゃあ大変よ。忙しいし、どうしてもイライラしちゃって夫婦でぶつかることもあるし」
「ええ……」
「いつだったかねえ、もう三十年以上前だけど、ちょうど五月や六月の、いま時分よ。派手な夫婦喧嘩しちゃって、もう家も店もどうでもいいやって思って、家出するつもりで駅の改札くぐったのよ」
でもね、とおばあさんは苦笑して、またツバメの巣を指差した。
「見つけちゃったの、あれを。ここよ、ここに座ってたら見つけたの。あの頃はまだ木のベンチだったんだけど、ああ、ツバメの巣があんなところにあるんだなあって……ツバメってのも忙しそうだなあ、夫婦で大変なんだなあ、って……」