メニュー
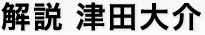 解説 津田大介
解説 津田大介
僕はインターネットユーザーのリテラシー向上や政策提言などを行う「インターネットユーザー協会(MIAU)」という活動をしているが、現実問題として寄付も有料の正会員数も当初想定していた以上に少なく、常駐の事務局員一人すらまともに雇えない経営状況が続いている。
それと実名の問題。
日本の読者がこの本を読んで驚くのは、アメリカではウェブ上では、自分の氏素性をはっきりと明示していることではないだろうか。
日本でも最初、ミクシィはアメリカにならって実名での登録を推奨していた。しかし、それが悪用されたことでその推奨をとりやめてしまった。飲酒の記述などいわゆる「犯罪自慢」をしていた大学生の実名が2ちゃんねるなどでさらされてしまう事態が続出したからだった。
また、日本の場合、会社に勤めるビジネスパーソンが実名を出すのは、メリットよりもリスクの方が大きいという問題もある。会社員が実名を出して活動すると、他人から副業禁止規定や、守秘義務違反などで足を引っ張られる。そういうことが現実に起きている。
ただ、そんな日本でも状況は変わりつつある。なによりもツイッターはそうした匿名主義を変える大きなインセンティブになっている。なぜならば、自分のバックグラウンドを明かさずに、つぶやくことは難しいから。自分のバックグラウンドを明かしてつぶやくことで、リアルのつながりも変わっていくことに人々が気がつき始めたから。
企業でも、たとえば朝日新聞の記者が個人的な感想を交えながらサッカーの試合をツイッター上で実況中継するのを認めるなど、パーソナルなバックグラウンドをむしろ出したほうがうまくいくと気がつき始めた企業もある。
この本は、ソーシャル・メディアの本場米国で長年オンラインの経験をオフラインの人間関係やキャリアに活かすことを身をもって実践してきた著者による、生きた「ソーシャル・メディア解説書」であり、使い勝手の良い指南書でもある。
豊富な事例を紹介し、事例から得られる教訓を紐解き、それらに基づいた原理原則をわかりやすく提示している。日本でウェブの力がわかり始めている人たちにとっては、指南書であると同時に強力な武器にもなる。
たとえば、あなたが、会社のなかで自分が企画にかかわった製品をSNSをつかってプロモーションをしたいと思ったとき、本書を上司に渡してみてはどうだろう。そうすれば、「わめく広告」に大金をはたいて、カスタマーサービスをないがしろにするといった会社の慣行も変わっていくかもしれない。
たとえ、会社がすぐに変わらなくてもいい、新しい価値を他人に教えることで、あなたの「ウッフィー」は確実に増えるのだから。
それが「ツイッターノミクス」の世界だ。
ソーシャルブックマーク