取材記「旅への招待」

その後も、重松さんの旅は続きました。
二〇〇八年三月、熊本県の阿蘇で、冬枯れの原野を焼き尽くす野焼きを。
二〇〇八年四月、奈良県・吉野町で、咲き乱れる三万本の桜を。
二〇〇九年三月、島根県・出雲市で、黄泉の国の神話を。
二〇〇九年六月、沖縄県・与那国島で、日本で最後に沈む夕陽を。
二〇〇九年八月十五日――。物語のラストシーンとなる長崎県・島原市をともに訪れました。
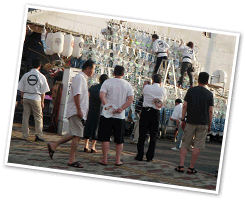
この日、島原では、初盆を迎えたひとを精霊船に乗せて、極楽浄土へおくる「精霊流し」が行われます。泊まった宿は、駅近くの古いビジネスホテル。チェックインをするために中に入っても、ロビーの灯りはついておらず、真っ暗なままでした。
部屋に荷物を置いた後、「すごい部屋だったなぁ。こんな古いホテルに泊まるのは久しぶりだよ。まいったまいった」と苦笑する重松さんと一緒に、街の中心へ。
夜の練り回しにむけて、町中の人が、思い思いの「切り子灯篭」を船に積んでいます。その様子を見ながら、「できた。これで書ける」と重松さんがつぶやきました。
旅の途中で、この背中を何度見たことでしょう。重松さんが紡ぐ物語は、旅とともに生まれていったのです。

その夜、町中が一つとなって、亡くなった人をおくる様子をみていると、私はまたも取材を忘れていました。出張の直前に、担当していた作家が突然亡くなってしまい、その人のことを考えると、涙が浮かんできたのです。
翌日、羽田空港で重松さんと別れる直前、こんなことを言われました。
「昨日、精霊流しを見て泣いていただろう。人の死に対して、そういう感性を持った担当者でよかったよ。最終回、もっと泣ける原稿を渡すから、待っとけよ」
最後の旅から二カ月後――。原稿が届きました。最終回の校了ゲラを読みながら、私はあふれる涙を止めることができませんでした。
編集部のデスクも、会社では読めないと思ったらしく、ゲラを外に持ち出していました。午前四時二十六分、私の携帯電話にメールが届きました。
「すごく泣いたよ。長い旅だったね」
年を重ねていけば誰しも、大切な人を喪うときが訪れるのでしょう。この物語は、大切な人の「死」を受け止めるための準備を、その「死」から歩き出すための原動力を教えてくれたような気がします。
長い物語を読み終えた今、舞台となった場所をもう一度訪れたい。そう思っています。