季節風|KISETSUFU
冬 サンタ・エクスプレス
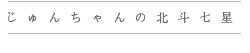
まったく面倒な奴だったなあ。いまでも思うし、あの頃はもっと思っていた。
でも、その苦労も、じゅんちゃんの笑顔を見ると報われる。
「わかった? 見えた? ね? ね? あそこだよ、あそこ」
空を指差したまま、僕を振り向いて笑うじゅんちゃんの顔は、ほんとうに、ほんとうに、幸せそうだったのだ。
*
じゅんちゃんが学校をクビになるかもしれない![]() と教えてくれたのは、野々村くんだった。三学期が始まって間もない頃のことだ。
と教えてくれたのは、野々村くんだった。三学期が始まって間もない頃のことだ。
冬休みに、河合先生と校長先生がじゅんちゃんの両親を学校に呼んで、これからのことを話し合ったのだという。年が明けて学校が始まってからも、話し合いはつづいているのだという。
なんで![]() とは、僕たちの誰も訊かなかった。やっぱりなあ、という顔になった友だちのほうが多かったと思う。
とは、僕たちの誰も訊かなかった。やっぱりなあ、という顔になった友だちのほうが多かったと思う。
その頃から、じゅんちゃんは学校を休みがちになった。給食のパンを届けに行っても、留守のことが多かった。
一月の半ばのある日、夜遅くになってじゅんちゃんのお母さんがウチを訪ねてきた。「おばさん、じゅんちゃんは?」と訊くと、両親に「あんたはもう寝なさい」「明日起きられなくなっちゃうぞ」と少し怖い顔で言われた。しかたなく自分の部屋に入り、布団にもぐり込んで、壁を隔てた居間の話し声に耳をすませた。団地の壁は、子どもの僕でさえ思いきり体当たりしたら壊れてしまうんじゃないかと思うほど薄っぺらだったが、おばさんも両親も低い声で話していたので、言葉はなにも聞き取れなかった。わかったのは、おばさんが泣いている、ということだけだった。
話が途切れたら、おしっこのふりをして、居間に行ってみよう。じゅんちゃんがほんとうに学校をクビになってしまうのか、寝ぼけたふりをして訊いてみよう。そう思っていたのに話はなかなか終わらず、まだかな、まだかな、と待っているうちに眠ってしまった。
翌朝、起きてすぐ母にゆうべのことを訊いてみた。母は「なんでもないの、子どもには関係ないの」としか言ってくれなかったが、朝刊を読んでいた父は、新聞から目を離さずに僕に言った。
「じゅんちゃんはいい子だからな、ずっと仲良くしろ」
「してるよぉ、僕がいちばん仲良しなんだもん」
父は、わかってるわかってる、と新聞を読んだままうなずいて、「でも、仲良くしろ。友だちなんだからな」と言った。
会話はそれで終わった。おとなになったいま記憶をたどってみても、父も母もくわしいことはなに一つ話してくれなかったはずだ。
なのに、父と交わした短いやり取りで、僕は答えのすべてを知った。ああ、じゅんちゃんはもうすぐいなくなるんだ、と思った。まるで真昼の空に星を見つけるみたいに、僕はじゅんちゃんとのお別れの日が近づいていることを悟ったのだ。
*
学校をクビになる![]() 。
。
ひどい言い方をしていた、あの頃の僕たちは。おとなになると、子どもの無邪気な残酷さがわかる。
河合先生とじゅんちゃんの両親の話し合いの内容も、おばさんが泣いていた理由も、いまならわかる。
じゅんちゃんは三学期が終わると転校した。家も引っ越した。僕たちの街よりずっと大きな、県庁のある街だった。
それが正しいことだったのかどうかは、おとなになっても、まだ、わからない。
*
じゅんちゃんは、星の中でも特に北斗七星が好きだった。「ほくとしちせい」という名前がカッコいいから、と言っていた。
転校することが決まったあと![]() 一月の終わり頃だったと思う。団地のベランダから、仕切り板を挟んで左右に分かれて夜空を見上げ、北斗七星の位置をじゅんちゃんに教わった。初めてのことではない。じゅんちゃんは星のことなら何度でも教えてくれるのだ。
一月の終わり頃だったと思う。団地のベランダから、仕切り板を挟んで左右に分かれて夜空を見上げ、北斗七星の位置をじゅんちゃんに教わった。初めてのことではない。じゅんちゃんは星のことなら何度でも教えてくれるのだ。
ほら、あそこと、あそこと、あそこと、あそこ……あいぼー、見えてる?
僕はいつものように、しばらく「うーん、どこ?」と探してから、「あった、わかったっ」と声をあげた。
じゅんちゃんは手すりに抱きつくようにつかまって、仕切り板からひょいと顔を出した。僕も顔を出して、二人で笑った。
じゅんちゃんは、自分がやったことや言ったことをすぐに忘れてしまう。このまえ北斗七星を教えてくれたのは、ベランダとは正反対![]() 団地の廊下で夜空を見上げているときだった。
団地の廊下で夜空を見上げているときだった。