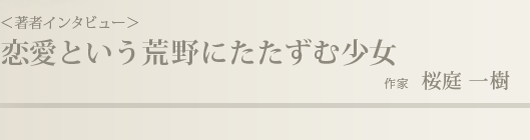『本の話』6月号に、『荒野』刊行にあたっての著者インタビューが掲載されました。その全文をご紹介します。


|
――直木賞受賞後第一作の『荒野(こうや)』は、以前ファミ通文庫で刊行された『荒野の恋第一部』『荒野の恋第二部』の二冊に、第三部を新たに書きおろして、一冊の本にまとめられました。恋愛小説家の父をもつ山野内荒野という少女が「恋」の存在を知って、少しずつ変化をとげていく物語です。この物語を書かれたきっかけからお伺いしたいと思います。
桜庭 それまでに書いたジュニア向けの『推定少女』や『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』が、生きづらい中学生や家族の問題とか、社会的な問題を入れたりしていたので、娯楽の要素が少なく深刻な話が多いから王道の恋愛小説をやってみないか、と編集者に言われたんです。自分はそんなに恋愛をメインにした小説を読まないし、恋愛は人生の中の一要素であって人はそれだけで生きているわけではないと思っていたので、恋愛だけで話を盛り上げるというのは難しいなと思いました。ミステリーが好きなので、恋愛をひとつの謎ととらえて、少女を探偵のようにもってきたらお話ができるかもと思ったんです。
――第一部は荒野が中学校に入学する日、電車のドアに制服を挟まれているのを、文庫本を熱心に読んでいた中学生の少年に助けられたところから始まります。このときの文庫が五木寛之さんの『青年は荒野をめざす』。荒野は、自分の名前がタイトルにつけられていると反応します。
桜庭 中学生を主人公にと考えたとき、自分がちょうどそのころ大好きだった吉野朔実さんの漫画『少年は荒野をめざす』を思いだし、また同時に五木さんの『青年は荒野をめざす』も読んでいたので、恋愛を書くにあたって主人公の名前が「荒野」というのはぴったりだなあと思ったんです。文庫版で書いていたときから、主人公の名前に意味を持たせるということはやっていて、『青年は荒野をめざす』の「荒野」というのは、青年がめざす人生だったり広い世界だったりするけれど、この子にとっては、恋愛が未知の世界だと思ったんです。『青年は荒野をめざす』のような登場人物の硬派な雰囲気が好きで、そこから思い出したのが高野悦子さんの『二十歳の原点』とかですね。当時好きな文章に線を引きながら夢中で読んでいました。『二十歳の原点』は、私の家の本棚に青春コーナーがあってそこに入るものなのですが、そこで発見したのが山口百恵さんの『蒼い時』や、中沢けいさんのデビュー作『海を感じる時』などです。主人公の「私はもっと○○にならなければいけない」などと言う青臭さがすごくいいんです。登場する女の子たちがお利口で、でも青くてまっすぐで、現代の子とは明らかに違うけれど、そういうのって今読んでもすごく面白いんじゃないかなと思い、話をちょっと古風な、昭和な雰囲気にしました。
――荒野と文庫少年、神無月悠也は同じクラスになりますが、荒野の名前を知ると、悠也はなぜか冷たくなります。それは荒野の父、山野内正慶に理由がありました。悠也は『青年は荒野をめざす』の一節から、荒野が“ハングリー・アートの子供”であると指摘します。小説もハングリー・アートであり、正慶は恋愛小説を書き続けるために、女という餌を食べては書き、書いては食べるという蜻蛉(かげろう)のような男だと言います。
桜庭 父親が恋愛小説家だと、大人の様々な恋愛をみながら、荒野自身が自分の恋愛についても考えられると思ったんです。ほうっておくと少女の恋愛から離れて、大人のどろどろした部分とか少女の成長とか違う要素のほうがたくさん入ってきてしまうので、意識して離れないように気をつけました。
――むかし美青年でいまなお美しく、女性読者に人気のある山野内正慶という作家は、本人がいたって真面目に言う気障なセリフもどこかユーモラスで、不思議な魅力があります。
桜庭 一部二部を書いているあたりでは、文芸の編集者や作家の方を知らなかったので、想像の中にある文豪のイメージのままで書いたんです。今こういう人がいたらある意味コスプレじゃないかと思いますが、離れで着物を着て万年筆で書いていたり、編集者が廊下で正座して待っていたり、編集長と囲碁をしたり。パーティでは夜の蝶が高校生の荒野の頬とかをつっついたりしていそうだなと……。書いている当時にこの文芸の世界を知っていたら、こうは書けなかったかもしれません。
――文豪つながりでいくと、このお話の中には夏目漱石の『吾輩は猫である』、内田百【門+月】の『ノラや』、正岡子規の句など、『猫』に関係するものが多く出てきます。
桜庭 荒野は猫タイプだと思ったんです。なつきそうでなつかない猫であったり、広がる山の中の荒野のイメージであったり、全体を統一したイメージで書きたかったので登場させる本もそうしました。
――今回の舞台は鎌倉ですが、鎌倉の街並や季節の移り変わりが丹念に描かれます。鎌倉を選ばれたのはなぜでしょうか。
桜庭 荒野のイメージや恋愛をする少女の話でと考えたときに浮かんできたのが鎌倉だったんです。今までの作品だと、どこだかはっきりしない地方都市とか「鳥取」などにしていたんですが、少女の恋をテーマにしたこの小説では、もっと読者にわかりやすい場所がいいんじゃないかと思いました。現在の平成の話だけれど、ちょっとレトロな雰囲気を出せるし、文豪っぽい小説家がいそうな情景もぱっと浮かび、小町通りなどは流行り廃りの激しい若者の町、たとえば原宿みたいな、ところもあります。渋い寺町というだけじゃなくて女の子の好きそうなものも多く入れられるので、絶妙なのかなと思いました。
――季節の描写とともに、全編を通して「匂い」も顕著です。面白かったのが、荒野は好きな人や気になる人を、洗濯物やひなた、日陰のやわらかい土のような、などといった多くの匂いで描写していますが、自分からみてよくわからない怖い存在という相手には匂いの描写がありませんね。
桜庭 『推定少女』の中で、義理のお父さんが怖いというときに、腐った柿のような匂いと表現したことがあって、嫌悪感には五感の感覚的なものがあると思っていたんです。今回の荒野は、家の中のことや義理の母親に対して、普通だったらすごく反発するのだと思うけれど、素直に受け入れます。人や物に対して、肯定的な子にしようと思って書いていたので、匂いもそうなのかもしれません。
――この三部作は、荒野の中学入学から高校の途中までが描かれています。一部で荒野が惹かれた悠也は遠く海を渡ってしまい、帰りを待つ荒野の前に、二部で、今度はまるで性格の違う、一見明るくてひょうきんな阿木くんという少年があらわれます。
桜庭 第一部を書き上げたときに、三部作にしてくださいと言われたんです。同じ季節でだらだら書くよりは変化をつけたいと思ったので、年齢をずらしたいと言ったら、編集者から毎回違う男の子と恋に落ちてほしいという要望があったんですね。ほかの男の子を出すのはいいけれど、毎回違う相手と恋愛するというのはどうかなと思ったので、片思いされる展開にしました。三部作にするのなら、まわりの大人たちの変化も書けるし、ちょっとの時間の差で十代の女の子はどんどん変わっていくはずだから、その変化が書けるかなと思いました。でもあんまり動かすと一部とは別人になってしまうので、三部を書くのがいちばん難しかったですね。
――荒野の友人たち、派手な美人顔の田中江里華や、陸上部で活躍する人気者の湯川麻美もそれぞれの恋をみつけていきます。三人というのもうまいバランスですね。
桜庭 女の子を三人並べて一番地味な子を主人公にしようと思ったんです。麻美は活発であんまり悩まずどんどんいくタイプで、江里華は異性を好まないマイノリティ、荒野はおくてですね。主人公を一人決めて、友達を出すことでその子の立ち位置がわかってきます。それぞれの成長のスピードがあるので、最初からすごく大人っぽかった江里華はそんなにかわらなくて、麻美のほうは彼氏ができたら大きな成長をみせ、荒野は少しずつ変化していくんです。
――徐々に子供から脱皮していく荒野ですが、義理の母、蓉子が妊娠中に正慶のまわりの女性に対してみせる嫉妬から、母と娘という親子の力関係が、明らかに逆転するのが印象的でした。
桜庭 女の子って、「おかあさん〜でしょ」みたいな対等の口をきく瞬間があって、母親がちょっと女である部分を見せたり、弱いところを見せたりするときに、言動に矛盾があることに気付いて、その瞬間に大人になるというか、母を乗り越えていくんだと思います。反対に母親は、娘が女として成長していくことに抵抗を感じることがありますよね。これは母と娘特有の関係のような気がします。
――三部を通して恋という要素のほかに「家」の存在が強く浮かびあがってきます。父親の女性関係から、家の中に不穏な空気が常にあったにもかかわらず、荒野は「家」に対して最初から諦観した概念を持っていますね。
桜庭 『推定少女』やほかの作品もそうなんですが、家から離れる家出少女とか、家というものを否定する子を書いてきて、同じことを書きたくないというのがあったので、違ったものをと、家に属する女という価値観で少女を書きました。でも私自身がそういう価値観をもっていたり、それを肯定したいわけでもないので、家に属して生きていくという女の子を書きながら、不思議な人だなぁと思っていました。
――ここに描かれているのは、荒野の十二歳から十六歳までの時間ですが、山野内家の大きな家の歴史というのがあって、その中の一部みたいな、家が主人公のような趣もありますね。
桜庭 『赤毛のアン』シリーズの一部みたいな……。お話って、出てくる人物がどのような人かというのは、その人の生きてきた時代がどんな時代だったのかとか、親はどんなだったのかとか、過去と無関係ではいられないから、話を書くのはその一部でも、書かれていない過去もあるし未来もあるんです。長い時間の流れがあるうちの、ここからここまで、とぴたっと切りとった一部のように書きたいんですね。先日、オペラの『トゥーランドット』を観にいったときに、ある国を出てきた主人公の王子様がどういう人かわからなくてすごく気になったんです。何の確執があって国を出てきたのか、どんなドラマがあったのかとか。人の作った劇などから、自分の作る話がわかるんだなと。過去が気になり、人との関わり合いでこういう人間になるのかというところに興味があります。主人公がとても強かったので、その裏の弱さと弱さの原因が知りたいと思ったんです。兄との確執があってとか、生まれや育ちとか、過去の弱さから強い人間になってとか、舞台を観ながら勝手に想像して作りこんでいました。荒野の場合は、接触恐怖症、なぜなら、とか、この家は歴史があって、などと作りこんでいきました。私は小説を書くときに、たとえば『赤朽葉家の伝説』の鳥取とか、『私の男』の紋別など、箱庭みたいに舞台を作っていくのですが、この小説の場合は鎌倉の家がそうだったように思います。人が出たり入ったり、追い出されたりまた会ったりで、家を主人公にしたら、ひとつの物語をずっと書き続けていけるんじゃないかと思ったくらいです。
(聞き手/「本の話」編集部)
『本の話』6月号に掲載