季節風|KISETSUFU
冬 サンタ・エクスプレス
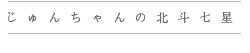
しょうがないなあ、と仕切り板から顔を引っ込めて笑った。しょうがないなあ、ほんと、うそばっかりついて、と笑っていたら、急に悲しくなった。
どんどんどん、と仕切り板を乱暴に叩いた。
「あいぼー、なに?」
のんきな声の返事を聞いて、もっと悲しくなってしまった。泣きたくなる悲しさではなく、怒りたくなる悲しさだった。
だから、僕は仕切り板をにらんで言った。
「うそつき」
じゅんちゃんは「はあ?」と聞き返した。板に隠れていても、きょとんとした顔が思い浮かんだ。
「こっちは南だから、北斗七星なんか見えないんだ、見えるわけないんだ、ばーか、うそつき」
悲しいから怒った。好きだから、嫌いになった。
でも、じゅんちゃんは怒り返さなかった。ひょっとしたら泣きだすだろうかとも思っていたが、はなを啜る音も聞こえてこなかった。
かわりに、あははっ、と笑った。
「こっちにもあるんだよ、あいぼー、知らなかった?」
だってほら、あそこだよ、あそこ、ひしゃくの形してるんだよ、北斗七星って、あそこ、あそこ、ひしゃくの形になってるだろ……。
仕切り板の外に、じゅんちゃんの腕が見える。人差し指が見える。
北斗七星は南の空には浮かんでいない。どんなに探しても見つかるわけがない。僕は知っていた。よーくわかっていた。
でも、悲しいまま見上げた夜空の星は、あれと、あれと、あれを結べばひしゃくになり、それと、それと、それと、それをつないでいっても、やっぱりひしゃくの形になった。
ひしゃくはたくさんある。大きなひしゃくも、小さなひしゃくも、縦長のひしゃくも、横長のひしゃくも……。星をどんどんつないでいけば、北斗七星もどんどんできた。
あははっ、と僕も笑った。
「ほんとだ」と夜空を見上げて、白い息を吐きながら言った。
「だろ? だろ? あっただろ?」
「うん、あったあった、北斗七星、こっちにもあった」
僕は仕切り板の外から、じゅんちゃんに手を差し出した。じゅんちゃんは、その手をぎゅっと握り返してくれた。
悲しかった。さっきよりずっと悲しくなった。でも、それは、怒りたくなる悲しさでも泣きたくなる悲しさでもなく、にこにこと笑うのがいちばん似合う悲しさだった。
*
じゅんちゃんが引っ越していったあと、一度だけ手紙を書いた。返事は来なかった。
次の年の正月に年賀状を出したら、転居先不明ではがきが戻ってきた。せっかく北斗七星の絵を描いたのに。
じゅんちゃんとは結局それっきり会っていない。あいつがその後どんな人生を歩んだのか、いまどんな暮らしをしているのか、僕にはなにもわからない。
ただ、星のきれいな真冬の夜、空を見上げると、じゅんちゃんのことを思いだす。
僕たちはみんな、同じ星空を見ている。じゅんちゃんが星をつないでつくる星座は、僕たちがつくる星座とはちょっと違っていたのだろう。いまでも違ったままかもしれない。
でも、僕たちが見ている星空は同じだ。
*
僕はゆうべ、学校の理科の宿題でオリオン座を観察するという次女に付き合って、夜空を見上げた。オリオン座を見つけたあと、「北斗七星って知ってるか?」と星を指差して教えてやった。
ほら、あそこと、あそこと、あそこと、あそこと……。
ちょっと横長のひしゃくが、北の空のてっぺんに浮かんだ。