季節風|KISETSUFU
夏 僕たちのミシシッピ・リバー
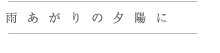
「あれえ? 先生、先生」
駅舎から出てきた若いグループが、はずんだ声で昭宏に声をかけてきた。
聞き覚えのある声に、あわてて顔を上げると![]() フリースクールの卒業生が、五人、そろっていた。
フリースクールの卒業生が、五人、そろっていた。
「……どうしたんだ?」
「いや、あのね、みんなで一回遊びに行こうかって言ってたんですよ。でも、五人全員OKっていう日がなかなかなくて、やっと今日、そろったんですよ」
五人のリーダー格だった生徒が言うと、残り四人もにっこりとうなずいた。
「おみやげもあるんですよ」と菓子工場に勤める女の子が紙の手提げ袋を得意そうに持ち上げる。「俺も、ほら、見て」と弁当工場に勤める男の子が鶏の唐揚げのパックを取り出した。「俺のみやげは食えないけど……」と大工さんに弟子入りした男の子は、「昨日、初めてカンナをかけさせてもらったんだ」と言って、カンナくずを見せてくれた。
高校に通う二人も、それぞれの学校の制服を着て、中学時代よりもずっと元気そうで、楽しそうで、幸せそうだった。
昭宏は「そうか、そうか……そうか……」と同じ言葉を三回繰り返して、五人の手を順に握った。思いがけない歓迎に五人の教え子たちは照れくさそうにうつむいてしまったが、そのぶん、昭宏の笑みは深くなる。
「今年もけっこう来てるんでしょ、新しい生徒」
「ああ……昔のきみたちのような子が、たくさんいる」
「先生も英語教えてるんだあ」
「ああ、教えてるぞ、うん、大変だけど、がんばってるぞ」
「ね、先生、そろそろ行かないと授業始まっちゃうでしょ、行こうよ」
菓子工場の女の子に手を引っぱられて歩きだしたとき、大工見習いの男の子が「おおっ、すげえーっ」と声をあげた。「ほら、あそこ、すげえよ」
西の空に夕陽がくっきり見えた。
朝の雨で空気の汚れが洗い流されたおかげか、ふだん見る夕陽よりもきれいに輝いていた。
「なあ……」
昭宏は夕陽を見つめながら、五人の誰にともなく言った。
「みんな、傘は忘れてないか?」
五人は怪訝そうに「はあ?」と顔を見合わせ、苦笑交じりに首をかしげながら、それぞれ「だいじょうぶでーす」「持ってまーす」と答えてくれた。
「そうか……傘は、大事だよな」
「はあ……」
「雨の日にお世話になった傘は、晴れた日でも大事だよな」
「ってか、よくわかんないけど……」
わからなくていいんだ。
いまはわからなくても、いつか、わかる。
そのときに![]() きみたちは、おとなになっているはずなのだ。
きみたちは、おとなになっているはずなのだ。
「よし行くか」
あらためて歩きだした。
高校に通う男の子が、ちょっと残念そうに「あーあ、ここで虹でも出てたらサイコーなんだけどなあ」と言った。
昭宏は、そうだな、と笑う。
だが、空に虹はなくてもかまわない。さっきからまぶたが熱い。ゆっくりと瞬いて、少しだけ目を開けると、まつげに小さな虹がキラキラと光っていた。