季節風|KISETSUFU
夏 僕たちのミシシッピ・リバー
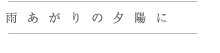
この三月、フリースクールで教えてきた五人の生徒が中学校を卒業した。五人とも、いじめに遭って学校に通う気力をなくしてしまっていた。それを必死に励ましながら、なんとか出席日数を確保して卒業までこぎ着けたのだった。
高校に進学したのが二人、就職したのが三人![]() よくやったぞ、と五人を褒めてやりたかったが、それはかなわない。
よくやったぞ、と五人を褒めてやりたかったが、それはかなわない。
五人は中学を卒業すると、フリースクールにはぴたりと顔を出さなくなった。
「それはそうですよ、だって、もう関係ないんですから」
数学を担当する仲間は苦笑交じりに言った。
「いったん巣立ったヒナは、もう元の巣には戻ってこないんです」
理科を担当する仲間も、さばさばと割り切っている様子だった。
昭宏も理屈ではわかっている。
なにもお礼をしてほしくてボランティアをつづけているわけではないし、国語の教師が言うとおり「便りのないのはよい便り」なのだろう、きっと。
それでも![]() 。
。
なんだかなあ、と思うのだ。
五人にとって、中学時代は、まさにどしゃ降りの雨つづきの三年間だった。フリースクールがせめてもの傘になっていた。だが、いまは彼らも新しい世界で元気にがんばっているはずだ。雨はあがった。傘は要らない。
わかっている。ほんとうに。
俺たちの傘をいま必要としている子どもたちは、彼らではない。どしゃ降りの雨に打たれている生徒のために、俺たちはがんばらないといけないんだ、と自分にも言い聞かせている。
それでも![]() 。
。
せめて元気にがんばってる顔ぐらい見せてくれてもいいのにな、と思うのも本音だった。
*
私鉄の駅で電車を降りると、ちょうど駅前のバス停からバスが発車するところだった。
フリースクールまでは徒歩で通っているので、ふだんなら気にすることもない光景だったが、乗車口のドアが閉まったとき、停留所のベンチにビニール傘が残っているのが、ふと目に止まった。
おいおい、忘れ物だぞ、忘れ物、と小走りにベンチに向かいながらバスに手を振ったが、運転手は気づかなかった。
駅前ロータリーを半周するバスを、思わず傘を手に走って追いかけた。
表通りに出る直前、やっとバスは止まった。
車内に駆け込んだ昭宏は、忘れ物の傘を頭上に掲げて、「これ、ベンチに忘れてましたよ」と乗客に声をかけた。立っているひとこそいなかったが、シートはあらかた埋まっている。しかし、昭宏の声に応えたひとは誰もいなかった。
「忘れものだったら、営業所に届けてください」と運転手はそっけなく言う。時間の遅れを気にしているのだろう。
昭宏は舌打ちして、もう一度、傘を大きく振りながら「いませんか? ベンチに置いてあったんですけど」と訊いた。
まだ返事はない。このバスの乗客が置き忘れたのではなく、もっと前から置いてあったのかもしれない。ふと思ったが、逆に引っ込みがつかなくなって、昭宏はさらにつづけた。
「誰かいないんですか? この傘、まだ新しいんですけど……」
うっせえなあ。後ろの席に座った若い男が言った。早く降りろよ、オッサン。吐き捨てるようにつづけ、昭宏をにらみつける。
声にこそ出さなくても、他の乗客も同じことを思っているのか、車内にはうんざりした空気が流れた。
むしょうに悲しくなった。
悔しくもなった。
たとえ持ち主がほんとうにいないのだとしても、自分の傘が手元にあるかどうか確かめようともしないのが、悲しくて、悔しくて、せつなくて……。
「この傘のおかげで雨に濡れずにすんだんじゃないんですか? 雨があがったからって、そんなにあっさり捨てていいんですか?」
思わず言った。
知らねーよ、そんなこと。さっきの男がまた憎々しげに言う。
運転手が「お客さん、乗るんだったら運賃入れてもらえますかあ」と声をかける。
「うるさい!」
これも、思わず怒鳴ってしまった。
と、そのときだった。
後ろの席に座っていた若い女性が、遠慮がちに立ち上がり、「すみません……」と消え入りそうな声で言った。「それ、わたしの傘だと思います……」
*
小さく、ささやかな、「事件」とも呼べないできごとだった。
それでも、忘れ物として処分されてしまうはずの傘が持ち主のもとに戻った。ビニール傘は、次の雨の日にも、また、彼女を雨から守ってくれるだろう。
バスを降りた昭宏は、ロータリーの歩道を軽い足取りで歩きだした。傘のためというより、自分自身のためにうれしかった。
そして![]() 。
。