季節風|KISETSUFU
秋 少しだけ欠けた月
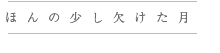
代わりに、アキラが飲んだ。自分の紅茶を三杯、母のティーポットからも二杯![]() 終わりたくない。終わらせたくない。
終わりたくない。終わらせたくない。
「ちょっと、アキラ。飲みすぎよ」
「だって……喉渇いてるんだもん」
「眠れなくなっちゃうぞ」
「だって……美味しいんだもん」
両親は、やれやれ、とため息をついた。そういうときのタイミングだけ、きれいにそろっていた。
アキラは母のティーポットに手を伸ばした。ポットにはまだあと一杯分の紅茶が残っているはずだった。
だが![]() 。
。
母は黙ってポットをアキラから遠ざけ、父はゆっくりと立ち上がった。
「帰ろう」
*
アキラはとぼとぼと両親のあとをついていった。席からテラスのドアまでかなり距離があるのがせめてもの救いだったが、それだっていつかは終わる。終わってしまう。終わったものは、もう二度と始まらない。
月を見上げた。満月じゃないんだな、とあらためて気づいた。まんまるからほんの少し欠けてしまっただけでも、それはもうまんまるではない。太陽のようにまぶしくもなく、星のようにまたたきもせず、ぽつんと夜空に浮かぶ月が、たまらなく寂しそうに見えた。
アキラは足を止めた。いや、勝手に止まってしまった。もう歩けない。足が先に進まない。並んで歩いていた両親は、アキラが立ち止まったことに気づいて、振り向いた。
「どうした?」と父が訊く。
「おなか痛くなっちゃったの?」と母が訊く。
違うよ、と首を横に振ろうとしたら、胸が急に熱いものでいっぱいになり、鼻の奥がツンとした。
両親は顔を見合わせる。今度は二人とも目をそらさなかった。父は苦笑いを浮かべて小さくうなずく。母も、そうよね、というふうにうなずき返す。
「アキラ、かげふみしようか」
母が言った。
「アキラが鬼だぞ、ほら、逃げるから追いかけてみろ」
父はおどけた足取りで駆け出した。
母も走る。笑いながら何度も後ろを振り向き、父とは違う方向に逃げる。
きょとんとしていたアキラは、やがて、あはっ、と笑って駆け出した。
追いかける![]() 父を。
父を。
追いかける![]() 母を。
母を。
父の影を踏んだ。母の影も踏んだ。だが、アキラは両親を追いかける。両親も「鬼を代わろう」とは言わずに、笑いながら逃げる。
テラスだけではおさまらず、芝生の中庭に出て、かげふみをつづけた。
室内のテーブル席にいた家族連れが、びっくりして窓の外を見ていた。アキラと変わらない年格好の女の子と、両親![]() 女の子はきれいなよそゆきの服を着ていたから、誕生日かなにかだったのかもしれない。そして、女の子は、やだぁ、と笑っていたから、アキラたち三人を仲良し家族だと思い込んでいるのかもしれない。
女の子はきれいなよそゆきの服を着ていたから、誕生日かなにかだったのかもしれない。そして、女の子は、やだぁ、と笑っていたから、アキラたち三人を仲良し家族だと思い込んでいるのかもしれない。
アキラは走る。父も走る。母も走る。父を追いかけて影を踏み、すぐに母を追いかけて影を踏み、また父を追いかける。
さんざん走って汗をかいた頃、アキラに影を踏まれた父は不意に足を止め、振り向いた。勢いのついたアキラの体は止まらずに、父に抱き取られた。
「つかまえたーっ」
父は息をはずませて、アキラを抱きしめた。
「つかまえたぞお、パパ、アキラをつかまえちゃったぞお!」
アキラは父に髪の毛をくしゃくしゃにされながら、「違うよ、つかまえるのは鬼のほうなんだよお」とふくれっつらで言った。
だが、父は笑って、さらに強くアキラを抱きしめる。母も走るのをやめて、アキラの背中にゆっくりと近づいていく。
月が三人を照らす。もうすぐ終わってしまう家族を静かに照らす。
やがて、影は一つになって、小刻みに揺れはじめた。