季節風|KISETSUFU
秋 少しだけ欠けた月
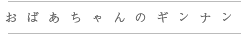
お母さんはイチョウの樹の前にたたずみ、色づいた葉っぱを見上げながら、「美沙に言われるまで忘れてたなあ、おばあちゃんのギンナンのことは」と言った。
「美味しかったよね、あのギンナン」
「そうねえ……昔はそれがあたりまえだったら気にしてなかったけど、そうそう、うん、おばあちゃんが亡くなってから、美味しいギンナンってあまり食べたことなかったね」
離婚の話には![]() ならない。
ならない。
「ほら、美沙、ここにギンナン落ちてるよ」
「どこ?」
「これよ、これ、あんたの足元にもあるじゃない、踏んだら臭いから気をつけなさい」
「あ、これかあ、なんかビワみたいだね」
「いままで見たことなかった?」
「うん……」
ふつうの会話がつづく。
思いのほかたくさん落ちていたギンナンを夢中になって拾っているうちに、言葉も途切れがちになり、やがてお母さんもわたしも黙り込んでしまった。
お母さんに心配をかけた。それはわかる。迷惑もかけちゃったんだろうな、とも思う。親戚やご近所に対して恥ずかしい思いも![]() してほしくないけれど、してしまうこともあるんだろうな。
してほしくないけれど、してしまうこともあるんだろうな。
でも、いまの沈黙は決して重苦しいものではなかった。むしろ逆に、口を開いてこの沈黙を破ってしまうのが、もったいない。
ギンナンを二十個拾った。半分は炒って焦げ目をつけて食べて、残り半分はギンナンごはんにしよう。下ごしらえのめんどうくささも、あの艶やかな緑色と、もっちりした歯触りを想像すれば、だいじょうぶ。においだって![]() もう一人暮らしなんだし。
もう一人暮らしなんだし。
でも、お母さんは口を閉めたポリ袋を「はい、ちょうだい」とわたしから取りあげた。
「殻をはずすとすぐに痛んじゃうから、殻付きで送ってあげるね」
「いいよ、そんなの、自分でやるから」
「なに言ってるの、狭いマンションでギンナンなんか干してたら近所迷惑でしょ」
田舎は家でも庭でも広いのだけがとりえなんだから、とお母さんは笑った。
*
一週間後、荷物が届いた。配達員さんが間違えたんじゃないかと思ったほど大きな段ボール箱の中には![]() ギンナンと、家の畑で穫れた野菜や、栗や、柿や、新米のお米や、お中元でもらったバスタオル……シャンプーとリンス、さらに五箱セットで特売だったティッシュペーパーまで入っていた。
ギンナンと、家の畑で穫れた野菜や、栗や、柿や、新米のお米や、お中元でもらったバスタオル……シャンプーとリンス、さらに五箱セットで特売だったティッシュペーパーまで入っていた。
でも、悪くない気分だった。箱に入っている品物よりも、それを一つずつ箱に詰めているときのお母さんの姿が、うれしい。
箱には、手紙も同封されていた。
〈ギンナンは一個だけ味見させてもらいました。とても美味しかったです。おばあちゃんの味でした。ギンナンは咳止めにもなるので、風邪をひきかけたら食べてごらん〉
やっぱり![]() 離婚の話は、なかった。
離婚の話は、なかった。
殻付きのギンナンをフライパンで炒って、ペンチで殻を割った。
つややかな緑色を見た瞬間、そう、これ、これ、これなの、と大きくうなずいた。
口に入れて噛みしめる。そう、これ![]() おばあちゃんと、お母さんのギンナンの味だ。
おばあちゃんと、お母さんのギンナンの味だ。
二つ目のギンナンの殻を割る。
お正月は、田舎に帰ろう。日帰りじゃなくて、泊まりがけで。
ギンナンを噛みしめる。一人暮らしの部屋の静けさが、ゆっくりと、ゆっくりと温もっていくのがわかった。