季節風|KISETSUFU
秋 少しだけ欠けた月
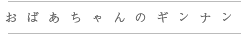
夫を戦争で亡くしたあと五人の子どもを女手一つで育てあげたおばあちゃんは、わたしがものごころついた頃には、もう腰が曲がっていた。
長男の源一伯父さんが家を継ぐと、おばあちゃんは隣の土地に小さな離れをつくってもらって、そこで一人暮らしをしていた。無口なひとで、苦労してきたせいなのか、愛想も悪かった。お母さんたち「嫁」は、おばあちゃんの前ではいつもびくびくしていた。
でも、わたしは、おばあちゃんが好きだった。八人いる孫の中で、おばあちゃんに一番かわいがってもらったのも、わたしだ。
「美沙はマイペースでしょ、おばあちゃんの顔色をうかがったりしないし、ずーっと黙ってても平気な性格だから、そこが気に入られたのよ」とお母さんはいつか言っていた。
確かに、おばあちゃんと二人で過ごす時間は、静かすぎるぐらい静かだった。ときどき思いだしたようにボソッとなにかしゃべって、言葉を一往復か二往復させて、また沈黙の中に沈み込む。テレビを観たり本を読んだりしていることも多かったが、そんな暇つぶしのネタもなく、ただぼんやりと黙り込んでいるだけのときもあった。それでも楽しかった。はしゃいで大騒ぎするような楽しさではなく、穏やかに安らぐ心地よさが、おばあちゃんと過ごす時間には満ちていたのだ。
懐かしい。いま、あらためて思う。
三カ月前に夫が家を出て、先月、離婚が成立した。二年足らずの結婚生活だった。最後の半年![]() 夫の不倫がわかってからの日々は、声を荒らげる喧嘩と互いに目も合わせない沈黙の繰り返しだった。罵り合いの喧嘩よりも、むしろ醒めきった沈黙のほうが、短すぎる結婚生活の苦い記憶として、胸に深く刻まれている。
夫の不倫がわかってからの日々は、声を荒らげる喧嘩と互いに目も合わせない沈黙の繰り返しだった。罵り合いの喧嘩よりも、むしろ醒めきった沈黙のほうが、短すぎる結婚生活の苦い記憶として、胸に深く刻まれている。
茶碗蒸しの中を探ると、二個目のギンナンがあった。今度もちっとも美味しくない。夫と過ごした最後の日々の、空虚でひえびえとした沈黙に似ていた。
*
不意に「美沙」とお母さんに声をかけられて、我に返った。
お母さんは兄貴の席に座って、「ちょっとあんた、今日帰っちゃうんだって?」と少し怒った顔と声で言った。
いろいろ忙しくて![]() と言い訳しようとして、ふと、思い直した。
と言い訳しようとして、ふと、思い直した。
「ねえ、お母さん……おばあちゃんって毎年ギンナンをくれたじゃない。あれ、どこで買ってたの?」
一瞬きょとんとしたお母さんは、「違う違う」と首を横に振った。「拾ってたのよ、自分で。熊野神社あるでしょ、あそこの境内に大きなイチョウがあるじゃない。そのギンナンだったの」
初めて知った。「そんなので食べられるの?」と聞き返すと、「だって、ギンナンなんて、べつに畑があるわけじゃないんだから」と笑われた。
「ね、じゃあさあ、熊野神社って、ここからだと車でどれくらいかかりそう?」
「はあ?」
「あと、ギンナンって、まだ落ちてる?」
拾いに行くつもりだった。タクシーに乗って出かけて、車を待たせたまま一つだけでもギンナンを拾って、駅に戻って……。
お母さんは「ギンナンって臭いのよ、あんたは売ってるのしか知らないから」と子どもじみた思いつきにあきれて笑い、それでも、真顔になって言った。
「連れて行ってあげようか」
*
タクシーに乗り込むと、親戚同士の付き合いから解放されたお母さんは、「あー、疲れた」と大きく息をついた。かえってわたしのほうが心配になって「途中で抜けちゃって平気なの?」と訊くと、「いいのいいの」と笑って、「みんなお酒が入ってるから、あれこれ言われちゃうと嫌だしね」![]() たぶん、わたしの離婚のことなのだろう。
たぶん、わたしの離婚のことなのだろう。
車の中では、お母さんは田舎の話ばかりした。今年は柿の当たり年だとか、タヌキが畑を荒らして困るとか、そんなことばかり。わたしにはなにも訊いてこない。離婚を事後報告ですませたことへの恨み言もない。こっちから話を切り出すのを待っているわけでもなさそうだった。
熊野神社でタクシーを降りてからも、変わらない。「絶対にギンナンは素手で触っちゃだめよ、ほんとに臭いんだからね」とくどくど言って、お店のひとに頼んで分けてもらった小さなポリ袋を、私に渡す。袋は二つあった。一つは拾ったギンナンを入れるための袋で、もう一つは手袋代わり。
「おばあちゃんもそうしてたの?」
「ゴム手袋だったかなあ、百個ぐらい拾ってたから、においもすごかったと思うよ」
ギンナンは拾っただけでは食べられない。水に浸して一晩おいて、果肉を剥いて、水洗いして、一週間ほど干して、それでやっと、おなじみのギンナンになる。果肉を剥くときのにおいは頭がくらくらするほどなんだから、とお母さんは教えてくれた。
おばあちゃんはずっと、毎年秋になるたびにそれをつづけていたのだ。売っているギンナンを買っても、それほど高い買い物ではないのに。旬のものではあっても、おなかの足しになるオカズというわけでもないのに。
ギンナンよりも、もっとふだんから愛想良くしてくれたほうがよかったのに、と思う。でも、無口で無愛想なおばあちゃんが、子どもや孫のために一人でギンナン拾いをしている姿を思い描くと、西の空に沈みかけた夕陽の色が、ひときわあざやかになる。